「やらなければいけないとわかっているのに、なぜか行動に移せない…」
このような経験は誰にでもあるのではないでしょうか。頭では理解していても、なかなか行動に移せないという悩みは、多くの人が抱える普遍的な課題です。一方で、思い立ったらすぐに行動に移し、次々と成果を上げていく人もいます。
この「すぐ行動する人」と「すぐ行動できない人」の間には、いったいどのような差があるのでしょうか?
本記事では、行動力の差が生まれる根本的な原因を脳科学的な視点も交えながら解説し、誰でも実践できる行動力を高めるための7つの具体的な方法をご紹介します。この記事を読むことで、あなたも「すぐ行動する人」への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
行動力は生まれつきの才能ではありません。適切な知識と方法を身につければ、誰でも「すぐ行動する人」になることができるのです。
それでは、まずは「すぐ行動できない人」の特徴から見ていきましょう。
1. すぐ行動できない人の5つの特徴
「わかっているけどできない」という状態に悩まされている方は多いでしょう。まずは「すぐ行動できない人」に共通する特徴を理解することから始めましょう。これらの特徴を知ることで、自分自身の行動パターンを客観的に見つめ直すきっかけになります。
1.1 完璧主義に陥りやすい
すぐに行動できない人の最も顕著な特徴の一つが「完璧主義」です。何事に対しても完璧で最高の状態を求める姿勢は、一見すると素晴らしい心構えのように思えます。しかし、この完璧主義が行動の大きな障壁となることがあります。
完璧主義の人は、一つ一つの小さな仕事に時間をかけ過ぎてしまう傾向があります。「もっと良くできるはず」「これでは不十分」という思いから、作業に終わりが見えなくなり、結果として他の仕事に着手するのが遅くなってしまいます。
また、完璧な結果を求めるあまり、失敗を極端に恐れる傾向もあります。「失敗したらどうしよう」という不安が先に立ち、行動そのものを先延ばしにしてしまうのです。
1.2 他者の利害関係を意識できていない
二つ目の特徴は、「関係する人の利害を意識できていない」ことです。私たちの仕事や活動は、ほとんどの場合、他の誰かと関わっています。上司、同僚、クライアント、家族など、自分の行動は必ず誰かに影響を与えます。
すぐに行動できない人は、自分の仕事や行動が他者にどのような影響を与えるかを十分に意識できていないことがあります。仕事が遅れることで、どのような影響が出るのかをイメージできないため、スピードを優先すべきか、質を優先すべきかの判断が適切にできません。
結果として、スピードを優先すべき業務にも時間をかけすぎてしまい、他の仕事が溜まっていくという悪循環に陥ります。
1.3 長期的な視点が持てない
三つ目の特徴は「長期的な視点が持てない」ことです。先延ばしにすることによって、タスクは次々と溜まり、最終的には大きなシワ寄せとなって返ってきます。
すぐに行動できない人は、目の前の仕事をいつまでに終わらせるべきかを明確にすることが苦手です。また、予期せぬ事態を想定することも不得意で、「後でやればいい」という考えが先行してしまいます。
長期的な視点を持ち、最終締め切りから逆算して計画を立てることができれば、先延ばし行動は大幅に減少するでしょう。
1.4 脳の準備不足状態にある
医学博士で「脳の学校」代表の加藤俊徳氏によれば、「すぐにやれないのは、脳の準備不足が原因」だといいます。脳科学的な観点から見ると、すぐ行動できない理由は脳の中に行動するための準備が整っていないからなのです。
人から言葉で指示されたことをすぐに実行できず思考停止してしまうのは、脳が「聞く」ための準備ができていないからです。耳から入ってきた情報がアタマの中に入っていかない状態では、情報を理解することができず、思考や行動が進まなくなります。
1.5 自信の欠如と失敗への恐れ
五つ目の特徴は「自信の欠如と失敗への恐れ」です。すぐに行動できない人は、自分自身に対する自信が不足していることが多く、「自分にはできない」「失敗するかもしれない」という不安が常につきまといます。
この自信の欠如は、過去の失敗体験や否定的なフィードバックによって形成されることが多く、行動を起こす前に様々な不安や懸念が頭をよぎり、結果として行動が遅れてしまいます。
失敗を恐れるあまり、行動そのものを避けてしまうことで、新たな経験や成長の機会を逃してしまうという悪循環に陥りやすいのです。

2. すぐ行動する人の5つの特徴
「すぐ行動できない人」の特徴を理解したところで、次は「すぐ行動する人」に共通する特徴を見ていきましょう。これらの特徴を知ることで、自分自身がどのように変わるべきかのヒントが得られるはずです。
2.1 自分自身に自信を持っている
すぐ行動する人の最も顕著な特徴は、「自分自身に強い自信を持っている」ことです。この自信は、必ずしも「自分は何でもできる」という過信ではなく、「やってみなければわからない」「失敗しても次に活かせる」という前向きな考え方に基づいています。
自信があることで行動のハードルが下がり、迷いなく行動に移すことができます。また、自信は行動の幅を広げ、その結果としてさまざまなチャンスに恵まれることになります。
チャンスを成功に変えることができれば、さらに自信がつき、「自信→行動→チャンス→成功→さらなる自信」という好循環が生まれます。このサイクルが確立されると、人生がより良い方向に進んでいくのです。
2.2 人生を楽しんでいる
二つ目の特徴は、「人生を楽しんでいる」ことです。すぐ行動する人は、仕事だけでなく、趣味や遊びなど様々な分野で積極的に活動しています。彼らは常に好奇心を持ち、新しいことに挑戦することを楽しんでいます。
この「楽しむ」という姿勢が、行動力の源泉となっているのです。楽しいと感じることには自然と行動が伴い、その結果として多くの経験を積むことができます。
多様な経験は視野を広げ、さらに新しい興味や関心を生み出します。このように、「楽しむ→行動する→経験を積む→さらに楽しむ」という循環が、行動力を持続させる原動力となっているのです。
2.3 適切な優先順位をつけられる
三つ目の特徴は、「適切な優先順位をつけられる」ことです。すぐ行動する人は、何をやるべきで何をやるべきでないのかを適切に判断することができます。
人間はマルチタスク、すなわち二つのことを同時にこなすと効率が悪くなることが知られています。すぐ行動する人は、この事実を理解し、一つのタスクを順にこなすことで生産性を高めています。
優先順位を明確にすることで、重要な仕事を後回しにする必要がなくなり、計画的に行動することができるのです。
2.4 行動の期待値の高さを理解している
四つ目の特徴は、「行動の期待値の高さを理解している」ことです。すぐ行動する人は、考えることから得られる経験値よりも、行動した結果得られる経験値の方が圧倒的に大きいことを知っています。
彼らは思考に時間を費やしてから一つの行動を起こすのではなく、多くのアクションを実験的に行うことを重視します。複数のアクションを行うことで、アクションの精度が上がり、最初は無駄が多くても少しずつ効率が上がっていきます。
結果的に、考えすぎる人よりも早く目標に到達することができるのです。
2.5 失敗を恐れず、成功するまでの速さが早い
五つ目の特徴は、「失敗を恐れず、成功するまでの速さが早い」ことです。すぐ行動する人は失敗を恐れません。むしろ、失敗を学びの機会と捉え、次の行動に活かすことができます。
失敗を恐れないことで、新しいことに挑戦するハードルが下がり、多くの経験を積むことができます。また、失敗から学ぶことで、次の行動がより効果的になり、結果として成功するまでの時間が短縮されるのです。
「失敗は成功の母」という言葉がありますが、すぐ行動する人はこの言葉を体現しているといえるでしょう。
3. すぐ行動することで得られる3つのメリット
「すぐ行動する人」と「すぐ行動できない人」の特徴を理解したところで、次はすぐ行動することで得られる具体的なメリットについて見ていきましょう。これらのメリットを知ることで、行動することへのモチベーションが高まるはずです。
3.1 時間を有効に使える
すぐ行動することの最大のメリットは、「時間を有効に使える」ことです。先延ばしにせずにすぐに行動することで、作業時間を十分に確保することができます。
私たちは心理学的に「現在バイアス」という傾向を持っています。これは、遠い将来の大きな利益よりも、目の前の小さな利益の方が大きく見えてしまう現象です。このバイアスにより、目の前の楽しみを優先して、重要な作業を後回しにしてしまいがちです。
しかし、作業を先延ばしにすると、結局は時間に追われることになり、十分な時間をかけられなくなります。一方、すぐに行動することで、作業時間を十分に確保でき、余裕を持って取り組むことができます。
また、作業が早く終われば、その分の時間を休息や他の活動に充てることができ、ワークライフバランスの向上にもつながります。
3.2 自己肯定感につながる
二つ目のメリットは、「自己肯定感につながる」ことです。やるべき仕事を後回しにすると、どうしても罪悪感や自己嫌悪に陥りがちです。
これらの負の感情は精神医学的に自己肯定感の低下につながり、QOL(Quality Of Life:生活の質)を下げてしまいます。QOLが低下すると生産性も低下し、さらに後回しにしてしまうという負のループに陥ってしまいます。
逆に、仕事を次々とこなすことができれば、達成感を得ることができ、自己肯定感が高まります。リズミカルに生活できるようになると、感じるストレスも軽減され、ゆとりを持った生活を送ることができるようになります。
自己肯定感の高まりは、さらなる行動力の源泉となり、好循環を生み出すのです。
3.3 周囲からの信頼を得られる
三つ目のメリットは、「周囲からの信頼を得られる」ことです。すぐに行動する人は、約束を守り、期限内に仕事を完了させる傾向があります。このような姿勢は、周囲の人々からの信頼を獲得することにつながります。
信頼されることで、より重要な仕事を任されるようになり、キャリアの発展にもつながります。また、信頼関係が構築されると、周囲からのサポートも得やすくなり、さらに効率的に仕事を進めることができるようになります。
「この人に任せれば安心」という評価は、ビジネスの世界でも私生活でも非常に価値のあるものです。すぐ行動する習慣を身につけることで、このような信頼を得ることができるのです。

4. 脳科学から見る「すぐ行動できる人」と「できない人」の差
これまで「すぐ行動する人」と「すぐ行動できない人」の特徴やメリットについて見てきましたが、この差はどこから生まれるのでしょうか。ここでは、脳科学的な視点からその違いを解説します。
4.1 脳の準備状態の違い
医学博士で「脳の学校」代表の加藤俊徳氏によれば、「すぐにやれないのは、脳の準備不足が原因」だといいます。脳科学的な観点から見ると、すぐ行動できるかどうかは、脳の中に行動するための準備が整っているかどうかによって決まります。
脳には1000億個を超える神経細胞があり、運動に関する細胞、聴覚に関する細胞、記憶に関する細胞など、同じ働きをする細胞同士が特定の部位に集まり基地を形成しています。この脳神経の集団がある基地のことを「脳番地」と呼びます。
脳番地は細かく分類すると120以上ありますが、大きくは8つに分類されます。この中で、「すぐ動ける」かどうかに最も関係しているのが「運動系脳番地」です。
4.2 運動系脳番地の活性化
運動系脳番地は、8つある脳番地の中で最も「すぐ動ける」かどうかに関係しています。赤ちゃんの脳もまず運動系脳番地から発達し、それに伴って他の脳番地も発達していきます。あらゆる脳番地と連携しているのが運動系脳番地なのです。
すぐ行動できる人は、この運動系脳番地が活性化されており、行動するための準備が整っています。一方、すぐ行動できない人は、運動系脳番地の活性化が不十分で、行動するための準備が整っていないのです。
脳科学的な観点から見ると、自分にとって得意なこと、好きなこと、日常的に繰り返していて習慣になっていることなどは、すぐにできます。これは、これらの行動に関連する脳番地が十分に発達し、活性化されているからです。
4.3 行動と脳の関係性
脳科学的観点から見ると、自分は「行動力がなく、すぐ動けない」と思っている人でも、いつも「すぐ動けない」わけではありません。ある場面では「すぐ動ける」こともあるのです。
これは、行動力が固定的なものではなく、脳の準備状態によって変わるからです。つまり、行動力は生まれつきの才能ではなく、脳の使い方次第で誰でも身につけることができるのです。
人から言葉で指示されたことをすぐに実行できず思考停止してしまうのは、脳が「聞く」ための準備ができていないからです。耳から入ってきた情報がアタマの中に入っていかない状態では、情報を理解することができず、思考や行動が進まなくなります。
しかし、脳の準備状態を整えることで、この状態を改善することができます。次のセクションでは、すぐ行動できるようになるための具体的な方法を紹介します。
5. すぐ行動できるようになるための7つの方法
ここまで「すぐ行動する人」と「すぐ行動できない人」の特徴や違いについて見てきました。では、実際にどうすれば「すぐ行動する人」になれるのでしょうか。ここでは、誰でも実践できる7つの具体的な方法をご紹介します。
5.1 ある程度厳格な予定管理を行う
すぐ行動するための第一歩は、「ある程度厳格な予定管理」です。予定を立てることで、何をいつまでにやるべきかが明確になり、行動の優先順位をつけやすくなります。
具体的には、以下のような方法がおすすめです。
- 1日の始まりに、その日にやるべきことをリストアップする
- タスクに優先順位をつける(重要度と緊急度で分類する)
- 各タスクにかかる時間を見積もり、スケジュールに組み込む
- 予期せぬ事態に備えて、余裕を持ったスケジュールを組む
ただし、あまりに厳格な予定管理は逆効果になることもあります。完璧なスケジュールを求めるあまり、計画を立てることに時間をかけすぎてしまっては本末転倒です。ある程度の柔軟性を持ちながら、予定管理を行うことが大切です。
5.2 完璧を求めすぎず、妥協点を見つける
二つ目の方法は、「完璧を求めすぎず、妥協点を見つける」ことです。完璧主義は行動の大きな障壁となります。「もっと良くできるはず」と考えて作業に終わりが見えなくなり、他の仕事に着手するのが遅くなってしまいます。
完璧を求めるのではなく、「十分に良い状態」を定義し、そこに達したら次に進むという姿勢が大切です。例えば、「80%の完成度で次に進む」というルールを自分で設定するのも一つの方法です。
また、「失敗してもいい」という心構えも重要です。失敗を恐れるあまり行動できないのであれば、小さな失敗を許容する姿勢を持ちましょう。失敗から学ぶことで、次の行動がより効果的になります。
5.3 考えるよりも先に行動する習慣をつける
三つ目の方法は、「考えるよりも先に行動する習慣をつける」ことです。考えることから得られる経験値よりも、行動した結果得られる経験値の方が圧倒的に大きいことを理解しましょう。
「考える→行動する」ではなく、「行動する→考える→改善する」というサイクルを意識することが大切です。まずは小さな一歩を踏み出し、その結果を見て次の行動を決めるという姿勢が、行動力を高めます。
具体的には、「5秒ルール」を活用するのも効果的です。これは、何かをしようと思ったら5秒以内に行動を起こすというルールです。5秒以上考えると、脳が様々な理由をつけて行動を先延ばしにしようとするため、素早く行動することが大切なのです。
5.4 小さな目標を設定して達成感を味わう
四つ目の方法は、「小さな目標を設定して達成感を味わう」ことです。大きな目標は時に圧倒的で、行動を起こすハードルが高くなってしまいます。そこで、大きな目標を小さな目標に分割し、一つずつ達成していくことが効果的です。
小さな目標を達成するたびに達成感を味わうことで、自己肯定感が高まり、次の行動へのモチベーションが生まれます。また、小さな目標は達成しやすいため、行動を継続するための原動力となります。
例えば、「1時間集中して作業する」「今日は3つのタスクを完了させる」など、具体的で達成可能な目標を設定しましょう。
5.5 「すぐやる」と声に出して自分に宣言する
五つ目の方法は、「『すぐやる』と声に出して自分に宣言する」ことです。声に出して宣言することで、自分自身に対する約束となり、行動を起こす確率が高まります。
また、「すぐやる」という言葉には強い力があります。「後でやる」と言うと、実際にはいつやるのか曖昧になりがちですが、「すぐやる」と言えば、行動するタイミングが明確になります。
声に出して宣言することで、脳に「今行動する」という強いメッセージを送ることができ、行動を起こすハードルが下がります。
5.6 行動のハードルを下げる工夫をする
六つ目の方法は、「行動のハードルを下げる工夫をする」ことです。行動を起こすハードルが高いと感じる場合は、そのハードルを下げる工夫をしましょう。
例えば、以下のような方法が効果的です。
- 作業環境を整える(デスクを片付ける、必要な道具を準備するなど)
- 作業の最初の一歩を極めて簡単にする(「ファイルを開くだけ」「5分だけ取り組む」など)
- 誘惑を排除する(スマホをサイレントモードにする、SNSをログアウトするなど)
- 行動のきっかけを増やす(リマインダーを設定する、目に見える場所にメモを貼るなど)
行動のハードルを下げることで、「始めるのが難しい」という心理的障壁を乗り越えやすくなります。
5.7 行動した自分を褒める習慣をつける
七つ目の方法は、「行動した自分を褒める習慣をつける」ことです。行動した後に自分を褒めることで、脳内で報酬系が活性化し、同じ行動を繰り返したいという欲求が生まれます。
小さな行動でも、「よくやった」「一歩前進した」と自分を認めることで、行動することへのポジティブな感情が強化されます。また、行動の結果だけでなく、行動したこと自体を評価することも大切です。
例えば、「完璧にできなかったけれど、行動に移せたことは素晴らしい」と自分を認めることで、次の行動へのモチベーションが高まります。
これらの7つの方法を日常生活に取り入れることで、徐々に「すぐ行動する人」へと変わっていくことができるでしょう。

6. よくある質問と回答
「すぐ行動する人」になるための方法について解説してきましたが、ここでは読者の皆さんからよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。これらの質問と回答を通じて、さらに理解を深めていただければ幸いです。
6.1 Q1: 行動力は生まれつきのものですか?
A1: 行動力は生まれつきの才能ではありません。脳科学的に見ると、行動力は脳の準備状態によって変わるものであり、適切なトレーニングや習慣づけによって誰でも身につけることができます。
脳には可塑性(かそせい)があり、使えば使うほど発達します。つまり、行動する習慣を身につけることで、脳の「行動する回路」が強化され、徐々に行動力が高まっていくのです。
また、自分は「行動力がなく、すぐ動けない」と思っている人でも、ある場面では「すぐ動ける」こともあります。これは、行動力が固定的なものではなく、状況や脳の準備状態によって変わることを示しています。
行動力は筋肉と同じで、使えば使うほど強くなります。小さな行動から始めて、徐々に行動の範囲を広げていくことで、誰でも「すぐ行動する人」になることができるのです。
6.2 Q2: 完璧主義を克服するにはどうすればいいですか?
A2: 完璧主義を克服するためには、以下のような方法が効果的です。
1. 「十分に良い」の基準を設定する:完璧な状態ではなく、「これで十分」という基準を自分で設定しましょう。例えば、「80%の完成度で次に進む」というルールを作るのも良いでしょう。
2. 小さな失敗を許容する:失敗を恐れるあまり行動できないのであれば、小さな失敗を許容する姿勢を持ちましょう。失敗から学ぶことで、次の行動がより効果的になります。
3. 完璧主義の根源を理解する:完璧主義の背景には、「失敗したら価値がない」「他者からの評価が全て」といった思い込みがあることが多いです。これらの思い込みを認識し、「失敗しても自分の価値は変わらない」「他者の評価だけが全てではない」と考え方を変えていきましょう。
4. 「完璧」と「優秀」の違いを理解する:「完璧」を目指すと、終わりのない作業に陥りがちです。一方、「優秀」であれば、十分に良い結果を効率的に出すことができます。「完璧」ではなく「優秀」を目指しましょう。
5. 段階的に取り組む:大きなタスクは小さな部分に分割し、一つずつ取り組みましょう。全体を一度に完璧にしようとするのではなく、部分ごとに「十分に良い」状態を目指します。
完璧主義を克服することで、行動のハードルが下がり、より多くのことに挑戦できるようになります。
6.3 Q3: 行動力を維持するコツはありますか?
A3: 行動力を維持するためには、以下のようなコツが効果的です。
1. 習慣化する:同じ時間に同じ行動をすることで、脳に「行動する回路」が形成され、自然と行動できるようになります。例えば、毎朝同じ時間に最も重要なタスクに取り組む習慣をつけるなど。
2. 環境を整える:行動しやすい環境を整えることで、行動のハードルを下げることができます。デスクを片付ける、必要な道具を準備するなど、小さな工夫が大きな違いを生みます。
3. モチベーションに頼らない:モチベーションは変動するものです。モチベーションが高い時だけでなく、低い時でも行動できる仕組みを作りましょう。例えば、「5分だけやる」というルールを設けるなど。
4. 自己報酬を設定する:行動した後に自分へのご褒美を用意することで、行動へのポジティブな感情が強化されます。好きな飲み物を飲む、短い休憩を取るなど、小さな報酬でも効果的です。
5. 進捗を可視化する:行動の成果や進捗を記録し、可視化することで、達成感を得やすくなります。チェックリストやアプリを活用して、自分の成長を実感しましょう。
6. 仲間を作る:同じ目標を持つ仲間と一緒に取り組むことで、互いに刺激し合い、行動力を維持することができます。定期的に進捗を報告し合うなど、互いにサポートし合う関係を築きましょう。
7. 目的を明確にする:なぜその行動をするのか、その先にどんな未来があるのかを明確にすることで、行動へのモチベーションが高まります。目的を定期的に思い出し、行動の意味を再確認しましょう。
これらのコツを日常生活に取り入れることで、行動力を維持し、「すぐ行動する人」としての習慣を定着させることができるでしょう。
7. まとめ
本記事では、「すぐ行動する人」と「すぐ行動できない人」の差について、様々な角度から解説してきました。ここで、これまでの内容を整理し、行動することの大切さを改めて確認しましょう。
7.1 本記事のポイント整理
まず、「すぐ行動できない人」の特徴として、以下の5つを挙げました。
1. 完璧主義に陥りやすい
2. 他者の利害関係を意識できていない
3. 長期的な視点が持てない
4. 脳の準備不足状態にある
5. 自信の欠如と失敗への恐れ
一方、「すぐ行動する人」の特徴としては、以下の5つを紹介しました。
1. 自分自身に自信を持っている
2. 人生を楽しんでいる
3. 適切な優先順位をつけられる
4. 行動の期待値の高さを理解している
5. 失敗を恐れず、成功するまでの速さが早い
また、すぐ行動することで得られるメリットとして、以下の3つを解説しました。
1. 時間を有効に使える
2. 自己肯定感につながる
3. 周囲からの信頼を得られる
脳科学的な視点からは、「すぐ行動できる人」と「できない人」の差は脳の準備状態にあることを説明しました。運動系脳番地の活性化が行動力に大きく関わっており、行動力は生まれつきの才能ではなく、脳の使い方次第で誰でも身につけることができるのです。
そして、「すぐ行動できる人」になるための7つの方法として、以下を提案しました。
1. ある程度厳格な予定管理を行う
2. 完璧を求めすぎず、妥協点を見つける
3. 考えるよりも先に行動する習慣をつける
4. 小さな目標を設定して達成感を味わう
5. 「すぐやる」と声に出して自分に宣言する
6. 行動のハードルを下げる工夫をする
7. 行動した自分を褒める習慣をつける
7.2 行動することの大切さ
私たちの人生は、行動の積み重ねでできています。どんなに素晴らしいアイデアや計画があっても、行動に移さなければ何も変わりません。「すぐ行動する人」になることで、人生の可能性は大きく広がります。
行動することで、新たな経験や知識を得ることができ、それが次の行動につながります。また、行動することで自信がつき、さらに行動しやすくなるという好循環が生まれます。
行動力は、ビジネスの世界でも私生活でも非常に価値のある能力です。「この人に任せれば安心」という評価は、信頼関係の構築やキャリアの発展にもつながります。
7.3 最初の一歩を踏み出す勇気
「すぐ行動する人」になるためには、最初の一歩を踏み出す勇気が必要です。完璧を求めず、失敗を恐れず、まずは小さな一歩から始めましょう。
本記事で紹介した方法を一つずつ実践することで、徐々に「すぐ行動する人」へと変わっていくことができます。すべての方法を一度に取り入れる必要はありません。自分に合った方法から少しずつ始めてみましょう。
最後に、行動力は一朝一夕で身につくものではありません。日々の小さな積み重ねが、やがて大きな変化をもたらします。今日から、「すぐ行動する人」への第一歩を踏み出してみませんか?
あなたの行動が、より充実した人生への扉を開くことを願っています。
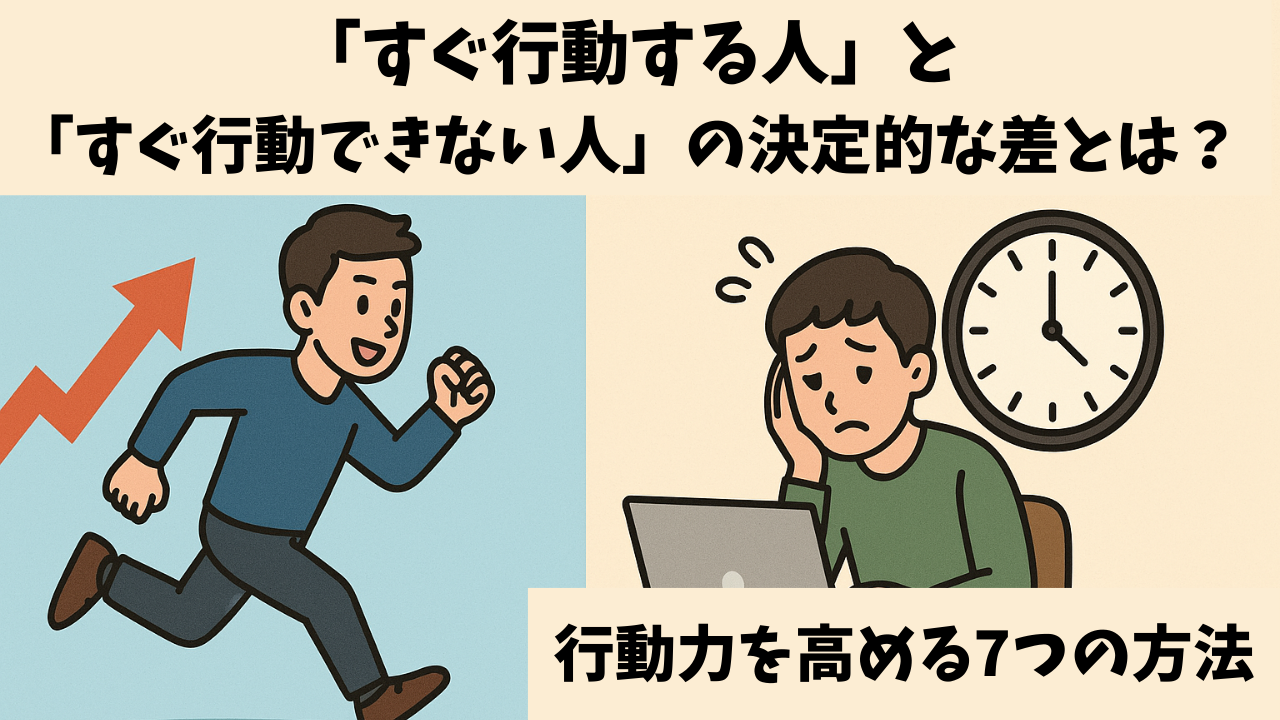

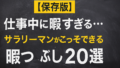
コメント